在宅サービスの場合
在宅サービスは、要介護度に応じて利用限度額(月額)が設定されています。一定所得以上の方は介護サービスの利用負担が所得に応じて2割または3割になります。なお、限度額を超えての利用については全額自己負担となります。
| 要介護度 | サービス利用 限度額(月額) |
自己負担額(月額) 1割負担 |
自己負担額(月額) 2割負担 |
自己負担額(月額) 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
注意:このほか、福祉用具の購入については年度内で10万円、住宅改修については原則1件につき20万円まで利用できます。
注意:施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。
施設サービスの場合
施設サービスは、要介護度と施設・居室の種類によって異なるサービス費用(利用金額)がかかります。また、サービス費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)に加え、食費・居住費・日常生活費の自己負担があります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)…生活介護が中心の施設
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
注意:新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方。
介護老人保健施設…介護やリハビリが中心の施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリを受けて、家庭への復帰を目指します。
特定入所者介護サービス費の支給
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。(給付を受けるには、市役所への申請が必要です。)
介護保険負担限度額認定については、毎年7月31日までの認定期間となっており、8月1日以降の認定については再度申請が必要となっております。ケアマネージャーや特別養護老人ホーム等への更新申請はしておりますが、ショートステイを利用している方へは更新案内はお送りしていないため、更新時期が来ましたら、市役所で更新手続きをお願いします。
- 制度の対象者
1.本人及びその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること。
2.本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること。
3.利用者段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと。
(注意)認定後、資産が基準額を超えた場合は対象外となりますので、必ずご連絡ください。
<収入・資産要件(令和7年8月から)>
|
段階 |
対象者 |
預貯金額等上限 |
|
|
第1段階 |
老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 |
1,000万円以下 (夫婦で2,000万円未満) |
|
|
第2段階 |
合計所得金額+課税年金額+非課税年金額が80万9千円以下の方 |
650万円以下 (夫婦で1,650万円以下) |
|
|
第3段階 |
1 |
合計所得金額+課税年金額+非課税年金額が80万9千円超120万円以下の方 |
550万円以下 (夫婦で1,550万円以下) |
|
2 |
合計所得金額+課税年金額+非課税年金額が120万円超の方 |
500万円以下 (夫婦で1,500万円以下) |
|
注意1:判定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金など)を収入として算定しますので、申請段階で申告してください。
注意2:配偶者がいる場合、世帯を別にしても判定の対象となります。また、内縁関係も夫婦としてみなします。
<1日当たりの費用負担額>
- 食費
|
段階 |
施設入所 |
短期入所 |
|
第1段階 |
300円 |
300円 |
|
第2段階 |
390円 |
600円 |
|
第3段階1 |
650円 |
1,000円 |
|
第3段階2 |
1,360円 |
1,300円 |
|
基準費用額 |
1,445円 |
1,445円 |
<1日当たりの費用負担額>
- 居住費(令和6年8月から)
|
段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (老健・医療院等) |
従来型個室 (特養等) |
多床室 (老健・医療院等) |
多床室 (特養等) |
|
第1段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
380円 |
0円 |
0円 |
|
第2段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
480円 |
430円 |
430円 |
|
第3段階1 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
430円 |
430円 |
|
第3段階2 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
430円 |
430円 |
|
基準費用額 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 |
1,231円 |
437円 |
915円 |
様式等
◯介護保険限度額認定申請
◯介護保険負担限度額認定について
高額介護サービス費の支給
1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。
| 利用者負担段階区分 | 区分 | 利用者負担上限額 | |
|---|---|---|---|
| 一般世帯(下記の区分に該当しない方) | 世帯 | 44,400円 | |
| 住民税世帯非課税 | 世帯 | 24,600円 | |
|
世帯・個人 | (世帯)24,600円 (個人)15,000円 |
|
|
世帯・個人 | (共通)15,000円 | |
注意:平成27年8月から、現役並み所得相当の方の限度額が44,400円に変更されます。
注意:対象となるときは、市から通知案内をします。
注意:保険料の滞納により給付が制限されている場合は、高額介護サービス費が支給されないことがあります。
注意:サービスにかかった利用者負担分を介護サービス事業者に支払った日から起算して2年を経過すると支給を受けられなくなります。
高額医療合算介護サービス費の支給(介護保険と医療保険の支払が高額になったとき)
同一世帯内で介護保険・国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算療養費制度)
注意:給付を受けるには、市役所への申請が必要です。
注意:同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)…計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間
| 基準総所得額による区分 | 限度額(年額) |
|---|---|
| 901万円超 | 212万円(176万円) |
| 600万円超から901万円以下 | 141万円(135万円) |
| 210万円超から600万円以下 | 67万円(67万円) |
| 210万円以下 | 60万円(63万円) |
| 市民税非課税世帯 | 34万円(34万円) |
| 区分 | 限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) | 67万円 |
| 一般(市民税課税世帯の方) | 56万円 |
| 低所得者(市民税非課税世帯の方) | 31万円 |
|
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 |
19万円 |
平成26年8月から平成27年7月の限度額は、経過措置が設けられています。()内の金額。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810

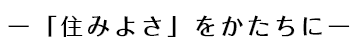
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。