児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。改正内容は以下のとおりです。詳細は、下部【手当(月額)】をご覧ください。
1.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の児童にかかる加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
2.所得制限限度額の引上げ
本人(受給者)の所得制限限度額を引上げます。
なお、今回の改正については、扶養義務者等の所得制限限度額についての変更はございません。
令和6年度現況届の対象者の方については、8月に現況届をご提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
制度概要
児童扶養手当制度とは、父母の婚姻の解消等により、父又は母と生計をともにしていない児童の親、あるいは親に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って手当を支給する制度です。
重要なお知らせ
平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)制度の運用が始まりました。これにより、児童扶養手当の手続きをする際には、個人番号カード又は通知カードと身元確認ができる書類を提示し、認定請求書や届出書に個人番号をご記入いただくことになります。
手当を受けることができる方(受給資格者)
手当を受けることができるのは、次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳未満)を養育している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している方です。
- 父と母が離婚した児童
- 父又は母が亡くなった児童
- 父又は母が一定の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 請求者でない、父又は母と生計を同じくしているとき
- 父又は母の配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)に養育されているとき
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
父又は母、養育者が次のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)と生活をともにしているとき 注意:受給資格者が父又は母の場合
公的年金等と児童扶養手当の併給について
- 申請者(受給者)または児童が公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給していて、年金の月額相当額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分が手当額となります。
年金の月額相当額が、児童扶養手当月額を上回る場合は、手当の支給はありません。 - 令和3年3月分から、申請者(受給者)が障害基礎年金を受給している場合、年金額ではなく、子の加算額と児童扶養手当額との差額分を受給できるようになりました。
手当(月額)
令和6年11月分から
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給停止 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 | 0円 |
| 2人 | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 | 0円 |
| 3人目以降 | 3人目以降 1人につき 10,750円を加算 |
3人目以降1人につき 10,740円から5,380円を加算 |
0円 |
一部支給の場合は、次の計算式により計算します。
手当額=45,500円-(注意1:受給者の所得額-注意2:全部支給所得制限限度額)×注意3:0.025
注意1:収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当分額を加算した額です。
注意2:所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、税の扶養親族等の数に応じて額が変わります。
注意3:第2子以降加算額の場合は0.0038561
| 税の扶養親族等の数 | 本人(受給資格者) 全部支給の 所得制限限度額 |
本人(受給資格者) 一部支給の 所得制限限度額 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
注意:本人(受給資格者)の所得が限度額内であっても、扶養義務者(本人から見て父母・祖父母・兄弟・子等の同居家族)等の所得が限度額を超える場合は、支給停止となります。
手当の支払日
認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
- 5月支給分(3月分から4月分)
- 7月支給分(5月分から6月分)
- 9月支給分(7月分から8月分)
- 11月支給分(9月分から10月分)
- 1月支給分(11月分から12月分)
- 3月支給分(1月分から2月分)
原則5、7、9、11、1、3月の11日に支給します。
支払日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、繰り上げて支給されます。
手当を受ける手続き
- 子育て推進課に認定請求書がありますので、直接お越しください。
- 認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なります。
この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されません。
認定後の届出義務
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、該当する場合は、すみやかに届出をしてください。
| 届出を必要とするとき | 届出書類等 |
|---|---|
| 毎年8月1日から8月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く) | 現況届 この届出がないと8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失います。 注意:所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届出をしてください。 |
| 手当を受け始めてから5年又は支給事由発生から7年を経過したとき | 一部支給停止適用除外事由届出書 この届出がないと手当が2分の1に減額となります。対象の方には通知が届きますので、現況届とともに8月中に届出をしてください。 |
| 対象児童が増えたとき | 額改定請求書 請求した翌月から手当額が増額されます。 |
| 対象児童が減ったとき | 額改定届 届出をした翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。 |
| 所得の高い扶養義務者と同居又は別居する等現在の支給区分が変更になるとき 修正申告等により過去又は現在の支給額が変更になるとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由が発生した翌月から変更になります。なお、過払いがあるときは返納することになります。 |
| 受給資格を喪失したとき | 資格喪失届 |
| 受給者が死亡したとき | 受給者死亡届兼未払い手当請求書 戸籍法の届出義務者が14日以内に届出をしてください。 |
| 手当証書をなくしたり、破損、汚してしまったとき | 証書亡失届兼再発行請求書 |
| 公的年金に関する変更があったとき(公的年金を受給できるようになったときや、受給している公的年金額が変更になったとき等) | 公的年金給付等受給状況届 支給額に関わりますので、判明しましたらすみやかに届出をしてください。 |
| 上記以外に届出内容に変更があったとき(氏名、住所、支払金融機関が変わったとき等) | それぞれの変更届 届出が遅れたり、届出をしなかった場合、手当の支払が遅くなることがあります。 |
資格喪失届について
届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当額を全額返還していただくことになりますので注意してください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても異性と同居する等の事実婚状態になったとき
- 児童又は受給者が死亡したとき
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父又は母が帰宅したとき(遺棄の場合は安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812

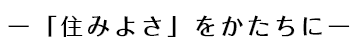
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。