虐待とは
- 子どもの虐待とは、親又は親に代わる保護者等により、子どもの心や身体にくわえられる、子どもにとって有害な行為のことをいいます。
- いくら子どものためと思ってやったことであっても、それが子どもにとって苦痛であり有害であればその行為は虐待といえるのです。
身体的虐待
児童虐待防止法第2条第1号:児童の身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加えること。
- 子どもに傷跡が残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせたり体に苦痛を与えることです。
- 例えば、殴る、蹴る、つねる、縛る、タバコの火やアイロンを押し付ける、冬の戸外に締め出す、首をしめる、逆さ吊りにする、激しく揺すぶったり振り回したりするなど。
- これらの行為は、心身に後遺症を残したり、最悪の場合には死に至らしめることがあります。
性的虐待
児童虐待防止法第2条第2号:児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること。
- 子どもに性的な嫌がらせをしたり、性関係を強要したりすることです。妊娠、中絶、出産などの結果を招いたり、異性への極端な嫌悪感や、自分自身への罪悪感等に取り付かれたりするなど、心身に深い傷を残します。
- 例えば、子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せるなど。
- しばしばもつれた人間関係を背景にもち、事実が明確になりにくいのが特徴です。性的虐待の多くは、女児に対してですが、男児も例外ではありません。
養育の拒否・放置(ネグレクト)
児童虐待防止法第2条第3号:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他保護者としての監督を著しく怠ること
- 子どもに適切な衣食住の世話をしないなど、子どもをほったらかしにすることです。
- 例えば、食べ物やミルクを与えない。衣服を与えない、家に閉じ込める、入れない。学校に行かせない。危険な場所に放っておく。乳幼児をおいたまま度々外出する。病気やけがをしても処置を施さない。極端に不衛生な環境で生活させる。など健康状態や安全を損なう行為。
- 極端な場合によっては、栄養障がいによる発育や発達の遅れをきたしたり、時には飢餓や脱水症状により、死に至らしめることがあります。
心理的虐待
児童虐待防止法第2条第4号:児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
注意:よく、しつけであるか、虐待であるか議論されますが、たとえ、しつけのつもりであっても、親の意図とは関係なく、子ども自身にとって有害かどうかで判断することが大切です。
- 心理的いじめのことで、子どもを情緒不安定にさせたり、心に傷を負わせることです。
- 例えば、子どもの存在を無視する、おびえさせる、罵声をあびせる、ひどい言葉でなじったりするなど。
- 心に傷を受けた子どもは、過度な不安、おびえ、うつ状態、無感動、無反応、強い攻撃性、習癖異常などの精神状態をしばしば現します。
こどもの虐待はなぜおきるのか
- こどもの虐待がなぜ、どのように起きるのかは大変難しい問題ですが、親自身が子どもの頃に虐待を受けたため子どもへの接し方がよくわからなかったり、夫婦の不和や仕事のトラブルなどのストレスに苦しんでいる場合に虐待に至りやすいと言われています。
- また、癇がきつく、なだめにくいとか、要求を強く表しそのことにこだわりやすいとか、子どもの性格などが引き金になって親の虐待を招くこともあります。
- 児童相談所に寄せられる虐待相談が急増している背景には、近年人間関係が希薄になり、子育てを行う親が孤立してしまっているという、子育てをめぐる環境の変化が大きく影響していると考えられます。
- 子育てに自信をなくし、不安感や焦燥感から虐待へと発展してしまうのです。したがって、虐待の発生を未然に防止するには、これから子育て不安に苦しむ親に対し、関係機関や近隣の人たちが協力し合いながら援助の手を差し伸べることが大切です。
- 虐待をする親はひどい人だと思われがちですが、親自身も悩み苦しんでいるのです。親を責めるだけでは何の解決にもなりません。虐待は、親からのSOSでもあるのです。
虐待に気づくために
下記のような兆候が見られる場合は要注意です。
子どもの様子
- 内出血によるアザやけががしばしば見られる。
- 服装、顔、髪の毛、手足などが極端に不潔である。
- いつもおなかを空かせている、食べ物への執着が強い、あるいは食が細すぎる。
- 表情が乏しい、態度がおどおどしている。
- 言葉遣いや態度があまりに丁寧である。(子どもらしさがみられない)
- 親の顔色をうかがう態度が見られたり、親と顔を合わせず、下を見たりしていたりする。
- 過度に乱暴だったり、弱いものへの暴力がひどい。
- 家に帰りたがらない、家出を繰り返す。
- 子どもがいるはずなのに姿がほとんどみえない。
- 性的なことに過度の関心がある。
親の様子
- 親の子どもへの態度やことばが拒否的である。
- 子どもをしょっちゅうたたいている。
- 子どもがなつかない。
- 子育てに疲れイライラし、子どもに当り散らしている。
- 食事や衣類などへの準備や配慮がない。
- 子どものけがや傷跡についての説明が不自然。
どこに相談すればいいのか
子育てに悩んだり、虐待されている子どもを発見した場合は、次のような機関にお気軽にご相談ください。
児童相談所
都道府県と指定都市に設置されており、18歳未満の子どものあらゆる問題について相談に応じています。児童福祉司や心理判定員、精神科医などの専門職がそれぞれの立場から調査や診断、指導を行います。また、必要な場合は、子どもを一時的に保護したり施設入所措置をとったりします。
- 山形県中央児童相談所(山形県福祉相談センター)
電話番号:023−627−1195
所在地:山形市十日町1−6−6 - 山形県庄内児童相談所
電話番号:0235−22−0790
所在地:鶴岡市道形町49−6
子育て推進課・最上総合支庁子ども家庭支援課
本市の子育て推進課には、家庭児童相談員が常駐し、児童問題を含め社会福祉全般の業務を行っています。最上総合支庁子ども家庭支援課には、児童相談所相談員が常駐し、相談業務を行っています。
- 新庄市子育て推進課
電話番号:0233−22−2111(547) - 最上総合支庁子ども家庭支援課
電話番号:0233−29−1281
保健所・新庄市保健センター・健康課
乳幼児検診や子どもの健康相談、栄養相談など、保健師などが専門的な指導を行っています。子どもの虐待の対応においてもこうした相談等の場を通じて重要な役割を果たします。
- 健康課健康推進室
電話番号:0233−22−2111(513・514)
新庄市地域子育て支援センター
地域の親からの育児相談、子育てサークルへの支援など、住民に身近な子育て支援を行っています。
- 新庄市子育て支援センター
電話番号:0233−22−5115
児童委員(主任児童委員)
児童委員は、民生委員を兼ねており、担当地域の家庭への援助や指導、福祉事務所や児童相談所への協力をします。主任児童委員は、区域を担当せず、専ら児童福祉に関する業務を担当します。
通告義務について
児童福祉法第25条:保護者のいない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認める児童を発見したものは、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。
- 虐待を発見した人は、児童福祉法に基づく通告の義務があります。実際に虐待であるかどうかは、通告をうけた機関が行います。
- 通告を受けた児童相談所や福祉事務所では、通告の内容や、誰が通告してきたかなどの情報を、その親などに教えたりすることはありません。通告についての秘密は守られます。したがって、通告者と親との関係をこわすことはなく、援助のつながりを作っておくことが可能です。
- 子どもは、自ら救いを求めることができません。あなたの勇気あるご一報が子どもの命と心を、親の人生を救うのです。
児童相談所等に相談すればどうなるのか
- 子どもの虐待の対応について中心的な役割を担っているのが児童相談所です。虐待について相談や通告があれば、児童相談所は、関係者と連携しながら、事実関係の調査を行い、緊急に子どもを保護する必要があるときは判断したときは、子どもを一時的に保護します。
- 児童相談所では、調査の結果や子どもの心理状態、性格、行動面などを考慮し、子どもにとって最も適切な手立てを決定します。具体的には、親子一緒に生活させながら家庭訪問や通所による指導を行う在宅指導や、子どもを児童福祉施設や里親に預けたり、他の適切な機関を斡旋したりします。
要保護児童対策地域協議会
- 虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。
- そのため市では平成18年4月、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として新庄市要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関と情報の共有化や支援の協議を行っております。
このページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画係
電話番号:0233-29-5811
保育推進係
電話番号:0233-29-5812

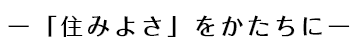
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。