目次
後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた国民健康保険や社会保険などの医療保険から、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。都道府県単位の広域連合が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務などを行います。
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で、一定の障がいのある方(申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受ける必要があります)
今まで加入していた健康保険から自動的に切り替わるので、加入手続きは不要です。
「一定の障がい」とは
- 国民年金法等障害年金1級、2級の方
- 身体障害者手帳1・2・3級の方及び4級の一部の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
負担割合
医療機関へ受診の際は、「1割」または「2割(一定以上所得者)」もしくは「3割(現役並み所得者)」を自己負担します。|
区分 |
対象者 |
|
3割 |
【現役並み所得者】
|
|
2割 |
【一般(一定以上所得)】 次の2つの条件を満たす方 1.世帯に住民税課税所得額が28万円以上の被保険者が1人でもいる。 2.世帯の被保険者の「年金収入【注2】+その他の合計所得金額【注3】」が以下に該当する方
|
|
1割 |
【低所得1】
【低所得2】 市県民税非課税世帯で、低所得1以外の方 など 【一般】 |
【注2】:年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
【注3】:その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
限度額適用認定証等について
令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での受診が基本となります。マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除になります。
令和6年12月2日から現行の限度額適用認定証の新規発行、再発行はできません。
マイナ保険証をお持ちでない方には、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
世帯の所得によっては申請不要の方もいますので、健康課国保医療係へお問い合わせください。
窓口負担割合が3割の方
|
負担 |
区分 |
1ヶ月ごとの限度額【*1、2】 外来・入院 |
|---|---|---|
|
3割 |
現役並み所得3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【*3】 |
|
現役並み所得2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【*3】 |
|
|
現役並み所得1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【*3】 |
【*1】保険適用外の医療費やおむつ、差額ベッド代などは含みません。
【*2】月の途中で75歳に到達した場合は2分の1の額になります。
【*3】「×1%」は実際にかかった医療費が「842,000円」「558,000円」「267,000円」を超えた場合、その超過額の1%を加算します。
窓口負担割合が2割・1割の方
|
負担割合 |
区分 |
1カ月ごとの限度額【*1、2】 |
食事代【*3】 (1食あたり) |
|
|---|---|---|---|---|
|
外来(個人ごと) |
外来+入院 |
|||
|
2割 |
一般 |
18,000円 令和7年9月30日までは自己負担増加額3,000円以内【*4】 |
57,600円 |
510円 |
|
1割 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
510円 |
|
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
240円 過去1年間の入院日数が90日以下の場合 |
|
|
190円 過去1年間の入院日数が90日超えの場合【*5】 |
||||
|
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
110円 |
|
【*1】保険適用外の医療費やおむつ、差額ベッド代などは含みません。
【*2】月の途中で75歳に到達した場合は2分の1の額になります。
【*3】療養病床に入院した場合の入院時生活療養費は上記表とは異なります。
【*4】令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は負担割合変更による自己負担額の増加額が3,000円までの上限となります。以下のページでも詳細をご確認ください。
医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担)について
【*5】90日を超える場合は「長期該当」となり、申請が必要となります。マイナ保険証の方でも申請が必要です。
医療費が高額になったとき
医療費一部負担金の合計が「1か月ごとの限度額」(上記表を参照)を超えたときは、超えた分の金額を「高額療養費」として支給します。
該当する場合は、後期高齢者医療広域連合より申請のご案内をお送りします。
保険料
保険料の額は、被保険者一人ひとりの所得に応じて次のように計算されます。
【所得割額】+【均等割額】=年間保険料
- 所得割額:所得に応じて負担
(前年中の所得-43万円)×(所得割率)
58万円以下の方× 8.68%
58万円を超える方× 9.43%
- 均等割額:加入者全員が公平に負担 47,600円
世帯の所得に応じて7割、5割、2割の軽減が受けられます。
賦課限度額
- 令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方…年73万円
- 令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方…年73万円
- 令和6年度に75歳に到達し、新たに後期高齢者医療に加入される方…年80万円
保険料について不明な点等ございましたら、税務課諸税係(0233-29-5536)までお問い合わせください。
保険料の納め方
保険料の納付方法は『年金からの天引き(特別徴収)』と『金融機関等で支払い(普通徴収)』の2種類があります。
原則として、『特別徴収』で納付していただきますが、年金の年額が18万円未満の場合や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。また、申し出により口座振替に変更することも可能です。
それぞれの納付方法については、税務課からお送りする保険料額決定通知書をご覧ください。
保険料の支払いが困難な場合はご相談ください
特別な理由がないまま滞納が長引くと、医療機関の窓口で一旦医療費全額を自己負担していただく特別療養費対象になる場合があります。
パンフレット等資料について
山形県後期高齢者医療広域連合HPに各種資料がありますので、そちらをご覧ください。
http://yamagata-kouiki.jp/siryo/rengo-kouho.html(山形県後期高齢者医療広域連合HP)
関連リンク
- 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792

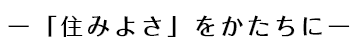
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。