予防接種は感染症からお子さんを守るために行われるものです。法で定められている予防接種(定期予防接種)は特にすすんで受けるようにしましょう。
接種方法
定められた対象年齢のときに、市内の指定医療機関(予防接種実施医療機関一覧)で接種を受けてください。定期予防接種は、それぞれ法で定められた対象年齢・標準的な接種間隔があります。対象年齢外の接種については、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
里帰り等の事情があり、市外での接種を希望する方はこちら
予防接種の種類
ヒブ小児肺炎球菌B型肝炎BCG四種混合五種混合麻しん風しん混合水痘日本脳炎1期ロタ
持ち物
- 母子健康手帳
- 予診票(接種票)
留意事項
- 新庄市から転出(住所移動)した場合は対象外となります。
- 市外(県内)の医療機関で接種を希望する場合や里帰り等の理由により、県外の医療機関で接種を希望する方は、健康課窓口で手続きが必要です。(くわしくはこちら)
- 転入された方は、母子健康手帳を持参し、健康課窓口へお越しください。
料金
無料
予防接種の種類
ヒブ
-
標準的な接種期間
初回:生後2か月から7か月までの間に、27日から56日の間隔をおいて3回接種
追加:3回目接種後7か月から13か月の間隔で接種
-
対象者
生後2か月以上5歳未満
小児肺炎球菌
- 標準的な接種期間
初回:生後2か月から7か月までの間に、27日以上の間隔をおいて3回接種
追加:生後12か月から15か月までに、3回目接種後60日以上の間隔をおいて接種 - 対象者
生後2か月以上5歳未満
B型肝炎
- 標準的な接種期間
初回:生後2か月から9か月までの間に、27日以上の間隔をおいて2回接種
追加:1回目接種後139日以上の間隔おいて接種 - 対象者
1歳未満
BCG
- 標準的な接種期間
生後5か月から8か月まで - 対象者
1歳未満
四種混合
- 標準的な接種期間
初回:生後2か月から12か月までの間に、20日以上の間隔をおいて3回接種
追加:3回目接種後、12か月から18か月の間隔をおいて接種 -
対象者
生後2か月以上7歳6か月未満
五種混合
- 標準的な期間
初回:生後2か月から生後7か月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回接種
追加:初回接種終了後から6から18か月の間隔をおいて接種 - 対象者
2か月以上7歳6か月未満
- 令和6年2月生まれ以降の方より、五種混合ワクチン接種票を配布しております。
- 令和6年1月生まれ以前の方で、五種混合ワクチンを希望する方は、健康課へご連絡ください。
- 四種混合ワクチン、ヒブワクチンを1回以上接種した方は、原則同じワクチンでの接種を行います。
麻しん風しん混合
- 接種期間および対象者
1期:生後12か月から24か月未満
2期:小学校就学前の1年間
水痘
- 標準的な接種期間
1回目:生後12か月から15か月まで
2回目:1回目接種後、6か月から12か月の間隔をおいて接種 - 対象者
1歳以上3歳未満
日本脳炎1期
- 標準的な接種期間
初回:3歳から4歳までの間に、6日から28日の間隔をおいて2回接種
追加:4歳から5歳まで - 対象者
生後6か月以上7歳6か月未満
ロタ
- 標準的な接種期間
初回接種は、生後2か月から出生14週6日後まで - 対象者(令和2年8月生まれから)
1価ワクチン:出生6週0日後から24週0日後までの間、27日以上の間隔をおいて2回経口接種
5価ワクチン:出生6週0日後から32週0日後までの間、27日以上の間隔をおいて3回経口接種
四種混合およびヒブワクチンから五種混合ワクチンへの交互接種について
令和6年4月より、五種混合ワクチン(四種混合にヒブワクチンが追加されたもの)の定期接種が開始されました。すでに四種混合ワクチンおよびヒブワクチンで接種を開始された方については、原則同一ワクチンで接種することが推奨されておりますが、ワクチンの供給不足などのやむを得ない事情がある場合には、残りの接種を五種混合ワクチンで接種すること(交互接種)が可能です。
なお、五種混合ワクチンの予診票は委託医療機関に設置しているものを使用できます。
長期療養により定期予防接種を受けられない方へ
長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特別の事情により対象年齢内に定期予防接種を受けられない場合、下記の要件により、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種することができます。
- 対象者
長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特別な事情によって対象年齢内に定期予防接種を受けられない方 - 接種期間
対象の病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から2年以内となります。ただし、BCGは4歳、四種混合および五種混合は15歳、ヒブは10歳、小児肺炎球菌は6歳未満までとなります。 - 手続き
予防接種を受ける前に申請が必要です。また、主治医からの意見書が必要となりますので、健康課へご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
健康課母子保健係
電話番号:0233-29-5790

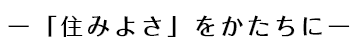
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。