令和4年度の市政運営に関し、私の所信を申し上げ、議員各位をはじめ、広く市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。
1.はじめに
いまだに収束が見えない新型コロナウイルス感染症ですが、世界的にワクチン接種が進み、感染者数は一時落ち着きを見せ、世界経済も回復の兆しが見えたものの、昨年末に確認された「オミクロン株」による新たな脅威にさらされております。
このような中、ロシアのウクライナ侵攻は、東西冷戦構造に逆もどりするのではないかと懸念されるところです。よく歴史は繰り返すと言われておりますが、戦争の歴史だけは決して繰り返してはなりません。日本政府もその立場で、冷静に会話による解決の糸口を各国に呼びかけて欲しいものです。
さて、国内では昨年2月から新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として本格的にワクチン接種が開始され、現在は3回目の接種が前倒しで行われています。本市においては、12月から3回目の接種がスムーズに進んでおり、医師会並びに関係機関の協力に対し感謝申し上げます。
国内経済においては、昨年1月に首都圏の4都県に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が再発令されて以降、全国各地で発令と解除を繰り返し、飲食店や観光業界では、今なお不安が拭えない状況にあります。
また、輸入木材の供給不足によるウッドショックや半導体不足により、建築業界や自動車・家電業界などでも大打撃を受け、その影響は一般家庭にも及んでおります。さらに、燃油価格の高騰が、コロナ禍から回復しつつある日本経済に大きな影響を与えております。
こうした中、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で1年延期となった、東京2020オリンピック・パラリンピック、先月開催された冬季北京オリンピックでの日本勢の活躍は、多くの国民と子どもたちに夢と希望を与えてくれました。
県内においては、新型コロナウイルス感染症拡大の第3波に見舞われた昨年3月、県独自の緊急事態宣言が発出され、飲食店に時短要請が出されました。そうした中、本市では飲食店やホテル・旅館業等に対し、独自の支援を行ってまいりました。
8月に入ると、各地域でクラスターによる感染が急拡大し、県内全域で「特別警戒レベル4」まで引き上げられましたが、その後は落ち着きを見せ、夜の会食などの人数制限が緩和されると、一時、飲食店等では活気を取り戻し始めました。しかし、12月31日に県内で「オミクロン株」が初めて確認されると、年明け1月には感染が急拡大、2月中旬からは本地域でも感染の広がりを見せ、医療現場や地域経済、家庭生活は、今なお大きな不安に襲われています。
一方、コロナ禍においても昨年の県内の雇用情勢は有効求人倍率が年間を通して上昇傾向にあるなど、改善が見られました。
本年1月の山形労働局の発表によりますと、昨年の春、県内で就職した高校生は16年ぶりに8割を超えたということで、高校生の目が都会から地元に向けられたことは一つの光明でありました。
また、県立新庄病院の移転工事が本格化し、躯体の全体像が明らかになってまいりました。同時に周辺の環境整備も令和5年の開院に合わせて準備が進められています。
東北中央自動車道は、「村山本飯田」「大石田村山」間が昨年12月11日に開通し、本年中に残りの区間も開通が予定されており、福島県相馬市から本市までの延長200キロメートルが1本の道でつながることになります。
本市における新型コロナウイルスの感染状況については、昨年4月上旬から8月上旬までは、一人も感染者が確認されませんでしたが、県内での感染が拡大し始めた8月中旬に、本市でも初めてクラスターが発生し、10月中旬までの2か月間で約100人が感染するなど、市民生活に大きな影響を与えました。しかし、市民の皆さまの「新しい生活様式」の取り組みへの協力により、市中感染拡大を抑えることができました。大切な人を守るためにも、引き続き市民の皆さま一人ひとりが新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めていただきますようご協力をお願いいたします。
一昨年、コロナ禍を受け戦後初めて中止となった新庄まつりですが、昨年2年ぶりに開催されました。特にまつり期間中は県内の特別警戒レベルが「レベル4」に設定されたため、規模を縮小し感染症拡大防止対策を徹底したうえでの実施となりました。
新庄まつりは、飢饉で疲弊した領民を励まし五穀豊穣を願うために行われたのが起源とされており、「コロナ禍」で疲弊した市民の皆さまにとって、改めて祭りの原点を振り返るきっかけとなり、新庄まつりへの熱い思いを感じることができました。
コロナ禍で暗い話題が多い中、本年1月19日の夕方、「しんじょう観光大使」第1号である作家の今村翔吾先生が、「塞王の楯」で、第166回直木賞を受賞したというビッグニュースが舞い込んできました。今村先生は、東日本大震災の災害ボランティアとして東北地方を訪れた際に、「新庄まつり」の起源に触れ、新庄藩を舞台とした江戸火消の活躍を描いた時代小説「羽州ぼろ鳶組」で作家デビューし、全国の読者を魅了しております。今村先生は「新庄は第二のふるさと」と言ってくださる程の新庄のファンであり、今後の更なるご活躍を期待しております。
昨年、令和4年から10年間の市土の利用計画を定める「第5次新庄市国土利用計画」の策定を進めてまいりましたが、これからの市土を見てみますと、昨年8月の新庄警察署の移転に続き、県立新庄病院の移転、県立高校の再編、さらに最上広域消防本部の移転が予定されており、今後数年間でまちの様相が大きく変化してまいります。また、新庄最上地域初の4年制大学である(仮称)東北農林専門職大学の開学を令和6年度に控えており、学術研究拠点としての発展も期待されます。そのため、必要な手立てをしっかりと整えていかなければならないと感じております。
地域の活性化では、市内の高校生の取組が話題を呼んでおります。最上地域の高校に通う生徒でつくる地域開発チーム「WATS」は、自主製作映画「想いよ届け」をこの度制作し、この3月に上映会を行うなど、動画による地域の魅力発信に積極的に取り組んでいます。さらに、現役高校生が会社の執行役員として経営に携わっている「フィエスタ」では革製のカバンを開発し、ふるさと納税の返礼品として採用されております。
また、新庄東高等学校の生徒の提案により「新庄蔵ぷりん」がオープンし、新庄神室産業高等学校の生徒とコンビニ大手「ローソン」が共同開発した「まるでラ・フランスみたいなパン」は、東北6県のローソンで1か月間限定で販売されました。さらに、ゆめりあに開設された鉄道ギャラリーにおいても同校の生徒によるジオラマ制作が進められており、2月26日には、8市町村のうち新庄市分のジオラマが完成しました。
このように、地元の若者たちによる地元の活性化への取組は、これからの若者の定住、起業に向けた取組につながるものと期待しており、本市といたしましても、若者の定住に向けた取組をこれまで以上に展開してまいります。
2.市政運営の基本的な考え方
以上、本市を取り巻く社会情勢を踏まえながら、令和4年度の市政運営の基本的な考え方について申し上げます。
私は、これまで、「人行きかうまち」、「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」をまちづくりの基本理念として掲げ、その実現に向けて、「経済力」、「地域力」、「教育力」を強化する施策を常に展開してまいりました。これら3つの基本理念を結び合わせた「地域基盤力」の向上により、地域の魅力を最大限に引き出し、元気で、人にやさしく、希望が持てる、「誰もが安心して暮らせる共生社会のまちづくり」に向けて引き続き全力で取り組んでまいります。そして、「新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」と昨年制定されました「新庄市手話言語条例」のもと、さらに「障がい者にやさしいまちづくり」を推進してまいります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大により、「新しい生活様式」が求められ、オンラインサービスやキャッシュレス決済の利用の増加などデジタル化の流れが急加速しております。
こうした社会背景を踏まえ、令和4年は、「デジタル化元年」として、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるためにデジタル技術の活用方針を定めた「新庄市デジタル化推進基本計画」に基づき、「市民サービスの向上」、「行政の効率化」、「地域の活性化」の実現を3つの柱として取り組んでまいります。
さらに、昨年から取り組んでいる「歴史的風致を活かしたまちづくり」については、令和4年度中に「歴史的風致維持向上計画」を策定し、国の認定を目指してまいります。令和7年度は新庄開府400年という記念の年を迎えます。本市の歴史的価値を再構築することで、「城下町新庄」の歴史や文化を後世に伝え、市民の誇りや郷土愛の更なる醸成を図ってまいります。
3.市政運営の指針
次に、市政運営の指針についてでありますが、市民憲章に謳われている「先人の築きあげた伝統を重んじ、新庄市民であることに誇りをもち、愛する郷土を発展させる」ことを目指し、「新庄市総合計画」と「新庄市行財政改革大綱」を基本に据え、財政規律を重んじながら、市政運営に取り組んでまいります。
市政運営の根幹である第5次新庄市総合計画では、成熟社会から文化創造の時代を迎えた今、これまで以上に「自分らしく豊かに暮らすこと」が大切な時代になると捉えております。新庄市の目指すべき将来像「住みよさをかたちに 新庄市」に向けて、市民一人ひとりが心の豊かさを実感できるまちを目指して、着実に計画を推進してまいります。
この将来像を実現するために、取り組むべきことをまちづくりの分野ごとに「子育て」、「教育」、「健康・福祉」、「産業」、「生活環境」、「都市基盤」の6つに分けて柱立てし、これらの施策を効果的・効率的に実施するため「シティプロモーション」と「行政経営」を横断的に展開してまいります。また、まちづくりにおける「重点課題」と「経営課題」の解決に向けた、全庁的に取り組むべきプロジェクトとして、「若者や子どもであふれるまちプロジェクト」、「市民が健康で元気なまちプロジェクト」、「持続可能で選ばれるまちプロジェクト」の3つを重点プロジェクトと位置づけ推進してまいります。あわせて人口減少克服と地方創生を目指す「第2期新庄市総合戦略」により、総合的な取組を推進してまいります。
次に、行財政改革でありますが、これからの行政運営は、限られた行財政資源を活用しながら、多様化・複雑化する行政課題へ柔軟に対応し、市民ニーズに即した良好な行政サービスを提供することで、市民満足度の高いまちづくりを進めることが、より一層求められております。
「第7次新庄市行財政改革大綱」の3つの基本方針、「効果的・効率的な行政システムの推進」、「活力ある組織と人材の育成」、「財政基盤の確立」を基本として、市民サービスの向上と行財政資源の確保に向け、取り組んでまいります。
次に、財政運営でありますが、これまで厳しい財政状況に対応するため、地方債残高や利息負担の軽減に努めるとともに、内部管理経費の削減、投資的経費の抑制等に取り組んでまいりました。
今後は、新型コロナウイルス感染症の影響等にも引き続き柔軟に対応しながらも、デジタル化の推進など、時代の変化に伴う新たな市民ニーズにも対応し、市政運営を停滞させることなく適切に対応しなければなりません。今後の人口減少を見据えながら、人口規模や歳入規模に見合った適正な歳出規模とするコンパクトな財政運営に努めてまいります。
4.重要課題に対応した令和4年度主要事業
次に、第5次新庄市総合計画に掲げる8つのまちづくりの柱、市全体で取り組む3つの重点プロジェクトに沿って、令和4年度の主要事業の概要を申し上げます。
はじめに、1つ目のまちづくりの柱「子育て 子どもの笑顔があふれるまち」ですが、母子保健事業をより一層推進することで、妊娠・出産支援の充実と子育て家庭に寄り添う支援の充実を図ってまいります。また、子どもたちが、安全で充実した保育環境の中で過ごせるよう、民間立保育施設等の施設整備に関する費用の一部を補助する「民間立保育所等施設整備費補助金交付事業」を実施してまいります。老朽化した中部保育所については、令和6年度の開所を目指し、新庄城址最上公園内に整備を行ってまいります。
子育て世帯の負担軽減を図るため、本年4月に小学校及び中学校等に入学する児童生徒に対し、「小中学校等新入学祝い金支給事業」を新たに実施いたします。また、現在実施している多子世帯保育料負担軽減、副食費負担軽減事業においては、第1子・2子の年齢要件を撤廃いたします。さらに国民健康保険税においては、15歳以下の子どもがいる世帯を対象に、子どもに係る均等割額を全額軽減いたします。
このほか、発達上の困難を有する児童の保護者や保育士等への支援策である「ペアレント・プログラム」等、乳幼児期からの特別支援活動事業の更なる充実を図り、子育て世帯の不安や負担が軽減され、地域の中で、子どもが健やかに成長することを目指してまいります。
2つ目のまちづくりの柱「教育 いのち輝き学びあうまち」では、社会を主体的に生き抜く力を育む学校教育を推進していくこととしています。GIGAスクール構想のもと、小中学生1人1台の専用タブレットを活用したICT教育を推進するため、ICT支援員を配置し、教員のスキル向上、授業支援、研修等のサポートを行い、児童生徒の情報活用能力の育成を図ってまいります。
また、特別支援教育体制の確立・強化のために特別支援教育センターを設置し、特別支援指導員を配置するとともに、個に応じた教育支援、保護者理解につなげてまいります。
地域に根差した学校づくりを推進するために、本市の特色ある小中一貫教育や地域とともにある学校づくりを実践してまいります。本年は、明倫学園のグラウンド等の外構整備に着手し、令和5年8月までの全工事完了を目指してまいります。
生涯にわたる学習機会の提供や青少年教育・家庭教育の推進、地域と学校との連携を推進するため、老朽化した八向地区公民館については、令和3年度末で廃止となる本合海児童センターに移転し、改修を行ったうえで、本年10月の開館を目指してまいります。
3つ目のまちづくりの柱「健康・福祉 健やかでしあわせなまち」では、新型コロナウイルスのワクチン接種について、変異株による感染が拡大している状況を受け、追加接種の前倒しを決定いたしました。また、接種対象年齢が引き下げられ、接種の開始時期もこの3月から予定されていることから、医師会や関係機関と調整し、接種を希望する方全員が迅速かつ安全に接種が受けられるよう進めてまいります。
生活習慣病の早期発見と重症化予防のため、特定健診や各種検診の受診率向上と保健指導を充実させるとともに、市民自ら健康づくりを実践していくことを目指し、引き続き「かむてん健康チャレンジ」事業に取り組んでまいります。
地域社会で孤立せずに地域コミュニティの一員としての「役割」や「生きがい」をもって暮らすことのできる地域福祉コミュニティの形成を推進し、多様化する支援ニーズに対して包括的な相談体制の構築を図ってまいります。そのため、令和5年度の支援体制構築を目指し、本年から重層的支援体制整備について、関係機関との協議を進めてまいります。そして、地域全体で支え合う共生社会の実現を目指してまいります。
高齢者が健康で生きがいをもち安心して暮らすことができるとともに必要とする介護支援が受けられるよう、高齢者福祉の推進に力を入れてまいります。また、障がい者が社会参画しやすい環境整備や日常生活を支える環境を整備し、障がい者にやさしいまちづくりに向け、障がい者福祉の推進を図ってまいります。
4つ目のまちづくりの柱「産業 活力のあるまち」では、農業経営の持続的な発展を目指すため、収益性の高い農業の実践を目指し、果樹園芸振興・畜産振興を柱として意欲ある担い手に対し支援することで、農業産出額の拡大を目指してまいります。
また、地域農業を支える担い手を育成・確保するため、担い手総合支援対策事業として、新規就農から農業経営の改善・発展まで一貫した支援を充実してまいります。
農林環境の保全として、「多面的機能支払事業」や「林道振興行政事業」による林道整備など、整備と適正な維持管理に取り組むことで、農地や森林が適正に管理され、多面的な機能が保たれるよう努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響を受ける事業者に対し、新たにキッチンカー等を活用した創業や事業拡大を支援することで市内事業者の販路拡大、経営力強化を図り、企業の経営安定と創業しやすい環境の整備を目指してまいります。
安定的な雇用を促進していくために、「人財育成推進・確保対策協議会」と連携し、働きやすい職場環境づくりに向けた支援をすることで、市内企業が就労先として選ばれるよう、特に若年層の人材確保に向けた取組を強化してまいります。また、雇用の場を確保するため、新たな工業用地の整備について検討を進めてまいります。
コロナ禍での開催となった昨年の「新庄まつり」ですが、感染症予防対策の徹底と新庄まつり実行委員会の熱意で無事成功裏に終えることができました。本年は通常開催できることを信じております。
また、令和7年度に新庄藩が開府400年を迎えることを全国にアピールするため、プレ事業として東京・巣鴨に山車を派遣します。
さらにこの度、信金中央金庫から企業版ふるさと納税として、寄附金をいただきました。この寄附金を活用して、新庄開府400年に向けて、「城下町新庄」の歴史的資源を活用し、市内の観光周遊促進に向けた事業に取り組んでまいります。
私の公約の一つである「道の駅」については、令和7年度のオープンに向けて、エコロジーカーデン周辺を国との一体型で整備することについて協議してまいります。
これまで検討されてきたインターチェンジ付近の「道の駅」については、本市が事務局となる8市町村による新たな組織で、今後、検討してまいります。
5つ目のまちづくりの柱「生活環境 安全・安心で美しいまち」ですが、近年、局地的な集中豪雨や地震等による被害が全国的に発生しており、防災・減災への関心が高まっております。大規模自然災害から市民の生命と財産を守り、安心した生活を実現するため、事前防災及び減災等に向けた施策に取り組んでまいります。
また、行政として、「公助」の充実を図りながら、市民の「自助」、「共助」を主体とする自主防災組織の育成と活動支援を行うため、「自主防災組織育成助成事業」を継続してまいります。
高浸水地域に位置している畑地区は、令和2年の豪雨災害により被災した数日間、飲料用水の供給ができなくなるなど、災害時の安定した供給が課題となっておりました。そこで本年、本合海地区から畑地区への送水を可能とするため、「本合海地区配水管布設及び橋梁添架工事」を実施し、インフラにおける防災対策の充実を図ってまいります。さらに、移動式の「排水専用ポンプ」を新たに2台配備し、本合海地区及び市内の内水氾濫に対応できるよう防災体制の強化を図ってまいります。
交通事故や犯罪が起きにくい環境が整備され、市民が安全・安心に暮らすことができるよう、交通安全・防犯活動の推進に力を入れてまいります。その中で犯罪や事件の未然防止と、発生した場合の二次被害を防止するために、本年は2次整備事業として、防犯カメラ8台を市内各所に設置してまいります。
生活環境の保全を推進するために、自然環境保全活動の推進や防犯灯のLED化更新補助事業を継続で行うことで、省エネルギー化やカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指し、自然環境の保全に対する市民の意識醸成と良質な生活環境が維持されるよう努めてまいります。
6つ目のまちづくりの柱「都市基盤 快適な暮らしを支えるまち」では、道路網の充実を図るため、日常的なパトロールや地域からの要望による市道の改修を行い、市道機能の保全に努めるほか、道路橋梁の劣化状況を把握し、計画的な維持修繕により長寿命化を図ることで、安全な道路環境の整備を目指してまいります。
今シーズンも、年末年始から大雪の日が続き、1月の殆どが、除雪作業に追われる日々が続きました。本市において克雪は長年の課題であり、その対策として冬季間の安全な交通確保と住民生活の維持を図るため、市道及び生活道路の除排雪の強化に努めてまいります。また、昨年好評だった「小型除雪機等購入費補助金」を継続し、雪総合対策事業の強化を図り、克雪対策の推進を図ってまいります。
令和2年度から見直しを進めてまいりました都市計画道路について、今後、廃止区間を含む路線について、都市計画変更手続きを進めてまいります。また、機能的で住みやすい市街地形成を目指すため、立地適正化計画に着手し、令和5年度を目途に都市計画用途地域の見直し作業を進めてまいります。そのうえで、緩やかな居住誘導として、整備されたインフラを有効活用し、空き地・空き家など市街地の空洞化解消に向けて取り組んでまいります。
市営バスまちなか循環線につきましては、順調に利用者数を伸ばし、徐々に市民に浸透してきているものと感じております。今後も安心して利用していただけるよう、安全な運行に努めてまいります。
地域公共交通の課題の一つである公共交通空白地域の解消に向け、2つのモデル地域でデマンド型乗合タクシーの実証運行を実施いたします。その他の地域につきましても関係機関と連携し、デマンド型乗合タクシーの導入に向けて協議を進めてまいります。
人口減少社会においても、安全・安心な水道水を安定供給するため、昨年10月、利用者の口径に応じた口径別料金体系に見直しを行っております。また、本年は水道料金等の支払いにおいて、コンビニ収納やスマートフォン収納を導入し、利用者の利便性の向上を図ってまいります。
県立新庄病院の移転に伴い、配水本管から病院までの管路を耐震化するため、「金沢地区配水管布設替工事」を行い、水道施設の計画的な整備・更新に努めてまいります。
生活排水処理につきましては、本市の普及率が県平均を下回っていることから、引き続き普及率の向上を図り、生活排水の適正処理を目指してまいります。
7つ目のまちづくりの柱「シティプロモーション 選ばれるまち」では、「市民が知りたいこと」、「市が知らせたいこと」がしっかりと伝わる戦略的な広報を推進し、本市の情報や魅力を広く市内外に伝えることで、市政への関心や参加意欲が高まり、本市への愛着や誇りが醸成されるよう、「伝わる」情報発信の充実に努めてまいります。その一つとして、スマートフォンに対応したデザインにリニューアルした市公式ホームページとLINEなどの多様な情報媒体による情報発信を強化します。
移住交流に向けた支援の充実を図るため、昨年12月に移住コーディネーターとして、地域おこし協力隊員が着任しました。関係機関と連携しながら、仕事や住まいに関する情報の提供など、移住促進のための情報発信の強化に取り組んでまいります。
8つ目のまちづくりの柱「行政経営 将来にわたって持続可能なまち」では、地域課題を地域と行政が連携して解決できる体制を整備するため、地域づくり活動を推進してまいります。
効果的・効率的な行財政運営を目指すため、「第7次新庄市行財政改革大綱」や「新庄市中期財政計画」などの個別計画に基づき、業務の効率化や健全な財政運営に向け取り組んでまいります。
私はこれまで、インフラ整備といえば道路や橋梁、上下水道など、ハード面が中心であったと感じておりますが、現在の高速化する情報化社会においては、「情報インフラ」の整備が重要であると考えております。
そこで、デジタル技術をより積極的に活用することで、市民サービスの更なる向上や業務の効率化に努めてまいります。
先行して、昨年12月から、市民課、税務課等の窓口で、複数のQRコード決済に対応できる、総務省統一QR「JPQR」を県内で初めて導入しました。これにより住民票などの手数料や施設使用料の支払いが、スマートフォンのアプリを用いて決済できるようになりました。
また、市営バスまちなか循環線と土内線・芦沢線では、冬期間の積雪状況により運行環境が悪化し、慢性的な遅延が発生している状況にありました。そのため、リアルタイムで運行状況が確認できるバスロケーションシステムを昨年11月から試験導入しており、本年4月からは、本格的に運用してまいります。
本年は、マイナンバーカードを利用することで、市役所に来なくとも、全国で住民票等各種証明書が取得できるよう、コンビニ交付の導入に向け準備を進めてまいります。また、社会教育施設では、オンラインイベントやオンライン会議が開催できるよう、施設のWi-Fi環境を強化してまいります。
このほか、先月からは、市民課、会計課両窓口において、来庁者のプライバシーの保護、窓口の混雑緩和、スムーズな案内を行うため、整理番号を表示し音声案内をする、広告付き番号案内表示システムを民間企業との連携により導入しております。
このように、市民サービスの向上を実現するために「デジタルトランスフォーメーション」等を推進し、市民ニーズに合った質の高い行政サービスの提供を目指してまいります。
また、今後の市庁舎建設に向けて、「庁舎建設基金」を設置し、将来予定される新庁舎建設のために、本年から積み立ててまいります。そのうえで、新庁舎建設に係る職員研修を実施し、訪れる誰もが利用しやすい庁舎となるよう研究してまいります。
これら8つのまちづくりの柱の事業とあわせ、まちづくりにおける「重点課題」と「経営課題」の解決に向け、3つの重点プロジェクトに全庁的に取り組んでまいります。
1つ目の「若者や子どもであふれるまちプロジェクト」では、「若者の地元回帰の促進」と「子どもを産み育てたいと思える環境づくり」、「郷土愛の醸成に向けた教育の推進」に取り組むことで、若者や子どもであふれるまちを目指してまいります。
2つ目の「市民が健康で元気なまちプロジェクト」では、「健康増進に向けた支援」と「生きがい創出・多様な活躍に向けた環境整備」、「介護予防の推進」に取り組むことで、市民が健康で元気なまちを目指してまいります。
3つ目の「持続可能で選ばれるまちプロジェクト」では、「戦略的広報の推進」と「行財政改革の推進」、「市民参画の推進」に取り組むことで、持続可能で選ばれるまちを目指してまいります。
5.おわりに
新年度を迎えるにあたり、市政運営に関する基本的な考え方と、主要な事業についての概要を申し上げました。
私は就任以来、一貫して「元気」と「やさしさ」があふれるまちづくりに取り組んでまいりました。近年は、「障がい者にやさしいまちづくり」を政策のキーワードに掲げ、そのために市役所として何ができるのか、職員自身が自分の職務において何ができるのかを常に考え行動するよう促してまいりました。その一つとして、まち中の公衆トイレなどバリアフリー化を進めております。
また、新型コロナウイルス感染症拡大により、「新しい生活様式」が求められ、オンラインサービスやキャッシュレス決済の利用の増加などデジタル化の流れが急加速しており、暮らし方や働き方も変化し、求められるまちの姿も変わってきております。
こうした社会背景を踏まえ、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるために、本年は、本市における「デジタル化元年」として、デジタル技術の活用と情報インフラの強化を進めてまいります。
そのうえで、デジタル技術を利用できる人も利用できない人も誰一人取り残されることのないよう努め、新庄市ならではの「住みよさ」をかたちにして、市民一人ひとりが心の豊かさを実感できるまちを目指していかなければなりません。そのためにも、職員一人ひとりが、高い意識を持ち、掲げた目標に向けて全力で取り組むことで、本市の課題を解決し、さらに、SDGs「持続可能な開発目標」にも取り組むことで、全ての市民にとって「やさしいまち」「安心して暮らせる共生社会」の実現につなげてまいりたいと考えております。
最後に、市民の皆さまの役に立つ所が「市役所」であります。「まちはだれのもの」と常に自らに問いかけ、「市民第一主義」を引き続き意識しながら、市民の皆さまにとって、本当に住みやすく住んで良かったと思えるまちを目指し、そして一日でも早いコロナ禍の終息を願い、職員一丸となり、市政運営に取り組んでいく決意を表明し、令和4年度の施政方針といたします。

このページに関する問い合わせ先
総合政策課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
電話番号:0233-22-2115
広報・地域づくり係
電話番号:0233-22-2116
システム統計係
電話番号:0233-22-2118

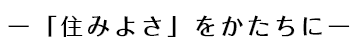
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。