令和5年度の市政運営に関し、私の所信を申し上げ、議員各位をはじめ、広く市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。
1.はじめに
世界中で感染拡大をみせた新型コロナウイルスは、中国で最初の感染者が発生して以来、これまで世界で6億7千万人以上が感染し、680万人以上の方が亡くなっています。また、発生から3年が経過し、日本を含め、世界各国は新型コロナウイルスとの「共存」を始めています。
昨年2月から始まったロシアによるウクライナ侵攻は、欧米の軍事支援、各国の経済制裁にも関わらず長期化し、今もなお戦闘の終結が見いだせない状況にあり、これを背景とする世界規模での食料・エネルギー価格の高騰は記録的な物価上昇をもたらし、エネルギーなどの供給構造の脆弱さを顕わにしました。
さて、国内では初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてから、陽性者累計数は3千万人を超え、あらゆる活動に様々な影響を与え続けてきました。昨年4月以降、感染拡大下においても、行動制限がないことを背景に、サービス消費を中心とする個人消費が回復し、政府はGDP(国内総生産)や企業業績はすでに新型コロナ前の水準に回復したとしています。
また、新型コロナをめぐる新たな動きとして、政府は感染症法上の位置づけを、季節性インフルエンザと同等の「5類」に移行すると決定しました。
国内経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあり、緩やかな持ち直しが続いています。一方で、ウクライナ情勢の影響を受けた資源価格の高騰や円安による輸入価格の上昇を背景に、食品価格や電気料金等の高騰が続いており、賃上げがインフレに追い付かず、個人消費が悪化に転じるリスクも高まっています。
こうした中、2022年のスポーツ界では、国内外での日本人の活躍が明るい話題となりました。メジャーリーグでの大谷翔平選手の偉業や日本球界では村上宗隆選手が日本人選手の最多本塁打記録を更新し、記憶に新しいところでは、サッカーワールドカップで森保監督が率いる日本代表が強豪国ドイツ、スペインを撃破し、日本中を熱狂の渦に巻き込みました。
国内の景気が緩やかに持ち直し続ける中、山形県の1月の経済動向月例報告では県内経済の総括判断も、雇用情勢の改善などにより「緩やかに持ち直している」としています。また、雇用環境は、県内の12月の有効求人倍率が1.62倍と好調な状況にあり、今年3月に卒業予定の県内高校生の就職内定率は、1月末で95.8%と高水準を維持しています。少子化や進学率の上昇で就職希望者が減る中、企業の人手不足感などを背景に求人数が増えています。
本市に関連する新たな動きとしましては、昨年10月に東北中央自動車道の東根北インターチェンジと村山本飯田インターチェンジ間が開通し、本市と首都圏が高速道路で直結しました。また、翌11月には泉田道路の開通により、国道13号とのダブルネットワークが構築され、通勤や救急医療など地域住民の利便性が向上し、近隣市町村や県を越える広域的な連携により、経済の活性化が図られるものと考えております。
また、県立新庄病院の移転改築工事が今年度内に完了し、新病院は令和5年10月1日に開院予定となっています。地域医療の中核として、住民の安全・安心を守る医療体制を提供いただいておりますことに感謝申し上げるとともに、住民の医療福祉向上のための連携を深めてまいります。
令和6年4月開学予定の東北農林専門職大学(仮称)は、最上管内初の4年制大学であり、市民の期待も大変大きいものとなっております。市といたしましても関係機関と連携し、大学との関係を深め、地域の課題解決と活性化に繋げてまいります。
本市における新型コロナウイルス感染症対策については、医師会並びに関係機関のご協力をいただきながらワクチン接種が滞りなく続けられており、また、市民の皆さまからは、新しい生活様式への取り組みにもご協力をいただいております。
多くの人命を救うために、懸命な治療にあたっていただいております医療従事者の皆さまに深く感謝申し上げるとともに、引き続き市民一人ひとりが感染拡大防止に努めていただきますようご協力をお願いいたします。
コロナ禍ではありましたが、昨年は、関係者の皆様のご協力により様々な行事が開催されました。5月には、新庄開府400年記念事業のキックオフイベントとして、観光大使である直木賞作家の今村翔吾先生に講演いただき、さらに、9月には今村先生が全国の書店を回る「今村翔吾のまつり旅」のゴールに新庄を選んでいただき、新庄市を全国にPRすることができました。
8月の新庄まつりでは、3年ぶりに通常開催の山車行列が行われ、多くの市民が、待ち望んだ新庄まつりの開催に勇気づけられたことと思います。また、新庄開府400年記念事業のプレ事業として、5年ぶりに東京都豊島区の巣鴨地蔵通り商店街に、神輿渡御行列の前揃いと山車2台を派遣することができ、沿道の観覧者からは、「新庄まつりは、遠くにいても心のふるさとである」といった声が聞かれ、改めて希望の祭りである事を実感いたしました。
令和7年度には、戸澤氏が新庄城を築城し領内を開いてから400年を迎えます。この新庄開府400年という記念すべき年を、「城下町 新庄」として栄えてきたこの地を発信する好機と捉え、市民と一体となって様々な事業を展開してまいりたいと考えております。
教育の日コスモスデーでの、「ふるさと学習発表会」や「いきいき夢ステージ」では、児童生徒の自由な発想に驚かされるとともに、活力ある発表に元気づけられました。
また、その他にも、市内において「そばまつり」、「味覚まつり」、「全国ねぎサミットinしんじょう」などのイベントが開催できましたことは、市民の皆さまに大変喜んでいただけたのではないかと感じております。
3年ぶりに行動制限がない年末年始となり、市内でも久しぶりの再会に笑顔があふれる光景が数多く見られました。今まで当たり前と思っていた日常生活の大切さを改めて実感するとともに、コロナ禍の行動制限により、人の交流が少なくなることが、経済活動と人々の暮らしに大きな影響を与えることも教えられました。
アフターコロナの中で、これからどのように関係人口を創出し、交流を深め、地域を元気にしていくかが重要と考えております。誰もがこのまちに住んで良かった、これからも住み続けたいまちづくりの実現に向け、市民の皆さまとともに、地域の諸課題の解決に取り組んでまいります。
2.市政運営の基本的な考え方
以上、本市を取り巻く社会情勢を踏まえながら、令和5年度の市政運営の基本的な考え方について申し上げます。
私は、これまで、「人行きかうまち」、「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」をまちづくりの基本理念として掲げ、その実現に向けて、「経済力」、「地域力」、「教育力」を強化する施策を展開してまいりました。引き続き、これら3つの基本理念を結び合わせた「地域基盤力」の向上により、少子高齢化社会に対応した「誰もが安心して暮らせる共生社会のまちづくり」、そして「障がい者にやさしいまちづくり」を推進してまいります。
また、新庄の将来を担う子どもたちを安心して産み育てられるように、多様なニーズに対応した「子育てしやすいまちづくり」を推進してまいります。子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくることができるように、子どもの成長に合わせて子育てを応援する施策を実施し、「将来のまちの担い手であるすべての子どもたちが、心身ともに健やかに成長することができるよう、社会全体で子どもたちを育むまちづくり」を進めてまいります。
市民憲章に謳われている「先人の築きあげた伝統を重んじ、新庄市民であることに誇りをもち、愛する郷土を発展させる」ことに通じます、「新庄市歴史的風致維持向上計画」が2月に国の認定を受けました。城下町である本市が持つ歴史的資源を積極的に活用した新庄らしいまちづくりの具現化に取り組み、市民の誇りと愛郷心を育て、私たちが受け継いだ、変わることのない新庄の歴史的価値を将来に繋いでまいります。
私は、成長の「昭和」、成熟の「平成」、そして「令和」の時代は、「文化創造」の社会に向かっていると考えております。成熟社会から、これまで以上に「自分らしく豊かに暮らすこと」が大切な「文化創造」の時代を迎え、市民一人ひとりが輝き、自分を表現し、文化を創造していくことのできるまちづくりに取り組んでまいります。
3.市政運営の指針
次に、市政運営の指針についてでありますが、令和5年度も引き続き「新庄市総合計画」を基本に据えて、市政運営に取り組んでまいります。
市民一人ひとりが、自分らしく豊かに暮らすことができるまちにしたいとの想いを込めて策定いたしました「第5次新庄市総合計画」をまちづくりの指針とし、新庄市ならではの「住みよさ」をかたちにして、市民一人ひとりが心の豊かさを実感できるまちづくりを推進してまいります。
将来像である「住みよさをかたちに 新庄市」を実現するために、取り組むべきことを「子育て」、「教育」、「健康・福祉」、「産業」、「生活環境」、「都市基盤」の6つのまちづくりの分野に柱立てし、これらの施策を効果的・効率的に実施するために「シティプロモーション」と「行政経営」を横断的に展開してまいります。
また、まちづくりにおける「重点課題」と「経営課題」の解決のため、3つの重点プロジェクトに全庁的に取り組んでまいります。
1つ目の「若者や子どもであふれるまちプロジェクト」では、「若者の地元回帰の促進」と「子どもを産み育てたいと思える環境づくり」、「郷土愛の醸成に向けた教育の推進」に取り組み、若者や子どもであふれるまちを目指してまいります。
2つ目の「市民が健康で元気なまちプロジェクト」では、「健康増進に向けた支援」と「生きがい創出・多様な活躍に向けた環境整備」、「介護予防の推進」に取り組み、市民が健康で元気なまちを目指してまいります。
3つ目の「持続可能で選ばれるまちプロジェクト」では、「戦略的広報の推進」と「行財政改革の推進」、「市民参画の推進」に取り組み、持続可能で選ばれるまちを目指してまいります。これら3つの重点プロジェクトとあわせて、「第2期新庄市総合戦略」により、人口減少の抑制による定住人口の維持と人口減少社会に対応した、誰もが元気で安心して住み続けられる環境づくりを推進してまいります。
行政運営は、限られた行財政資源を活用しながら多様化・複雑化している行政課題へ柔軟に対応し、市民ニーズに即した良好な行政サービスを提供することにより、市民満足度の高いまちづくりを進めることが求められております。そのため、「第7次新庄市行財政改革大綱」に基づき、効果的・効率的な行政システムの推進、活力ある組織と人材の育成、財政基盤の確立に向けて取り組んでまいります。
財政運営では、これまで、厳しい財政状況に対応するために、地方債残高や利息負担の軽減、内部管理経費の削減、投資的経費の抑制などに取り組んでまいりました。新型コロナウイルス対応や燃料・物価高騰は、今後の財政運営にも大きな影響を及ぼすことが見込まれますので、引き続き、国の経済対策の動向を注視しながら、限られた財源を有効に活用し、将来にわたり安全かつ良質な公共サービスを効率的に提供できるように、持続可能な財政運営に努めてまいります。
4.重要課題に対応した令和5年度主要事業
次に、第5次新庄市総合計画に掲げる8つのまちづくりの柱に沿って、令和5年度の主要事業の概要を申し上げます。
はじめに、1つ目のまちづくりの柱「子育て 子どもの笑顔があふれるまち」では、子育て世帯に寄り添う支援の充実を図ってまいります。
これまでの「小中学校等新入学祝い金支給事業」、「15才以下の子どもがいる世帯の国民健康保険税の均等割額の軽減」、「多子世帯の保育施設保育料負担軽減・副食費負担軽減事業」を継続し、「子育て支援医療給付事業」については、医療費の無償化の対象を高校3年生までに拡充します。また、「学校給食費補助事業」については、義務教育期間に2人以上の児童等が在籍している世帯の、第2子の給食費を半額、第3子以降の全額補助を新たに実施し、子育てに係る幅広い期間において子育て世帯の経済的負担を軽減いたします。あわせて、三世代同居、近居のための住宅を取得する子育て世帯に対し、費用の一部を助成する「三世代同居等住宅取得助成事業」を実施し、家族の支え合いによる子育てしやすい環境づくりを推進してまいります。
老朽化が著しい中部保育所については、歴史的風致維持向上計画に沿ったまちづくりの一環として、最上公園内の一角に新たに整備いたします。また、泉田保育所については、地域等のご意見を伺いながら、引き続き施設の整備の方向性を検討してまいります。老朽化が著しい、日新放課後児童クラブについても、安全に運営ができるよう、施設の整備についての検討に着手いたします。
保育施設は、子どもたちにとって、生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な場でありますので、安全で充実した保育ができる環境の整備を進めてまいります。
また、妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対応するため、子育て世代包括支援センターと地域子育て支援センターなどの相談窓口機能を充実し、きめ細やかな相談支援により、妊娠、出産、子育てに対する不安の解消を図ってまいります。
国においては、急速に進展する少子化を先送りできない課題と捉え、少子化対策を推進するとしています。本市においても、これからのまちづくりに、常に少子化対策という視点を持ちながら、教育分野を含め横断的に少子化への取り組みを展開してまいります。
2つ目のまちづくりの柱「教育 いのち輝き学びあうまち」では、児童生徒が意欲的に学び合い、生きる力を身につけられることを目指し、社会を主体的に生き抜く力を育む学校教育を推進してまいります。
そのために、「個別支援事業」、「教育相談・不登校適応教室指導事業」、学校司書や協働活動支援員の配置、特別支援センター設置による特別支援指導員を配置し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導と支援により、生きる力を支える学力の育成を図ってまいります。
また、児童生徒が安全・安心に学校生活を送ることができ、学習に必要な教育環境を充実させるために、学校施設・設備等の整備を進めてまいります。令和5年7月には、義務教育学校「明倫学園」の全ての工事が完了し、8月に「竣工式」を開催する予定であります。引き続き、本市の特色でもあります小中一貫教育の推進に全力で取り組み、学校と地域とが協働し、地域とともにある学校となることで、子どもたちが生まれ育ったこの地に関心を持ち、地域の良さを理解し、ふるさと新庄への愛着が育まれることを目指してまいります。
文化財に関しては、保存活用と継承のため、国指定重要文化財であります「旧矢作家住宅」を、専門家などの指導を仰ぎながら、適切な補修を行い、貴重な文化資源として後世に引き継いでまいります。
本市固有の歴史や文化を守り育て、次世代に継承していくため、歴史的風致維持向上計画に基づき、「歴史的建造物の保存活用」、「歴史的建造物周辺の環境整備」、「活動の継承及び担い手の育成・確保」、「歴史的風致の認識向上」、「歴史的風致を生かした観光振興」などに取り組み、城下町新庄に相応しいまちづくりを推進してまいります。さらに、学校教育や社会教育を通して、本市の歴史や文化、自然などについて学ぶ機会を充実させ、特に、子どもたちが地域の伝統行事や民俗芸能などについて興味・関心を持つことにより、愛郷心の醸成を図ってまいります。
3つ目のまちづくりの柱「健康・福祉 健やかでしあわせなまち」では、これまで65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザワクチン接種費用の助成対象に、生後6カ月から15歳までの子どもを追加し、インフルエンザによる重症化の予防策を強化いたします。
また、少子化対策として、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するために、不妊治療費の一部を助成いたします。
疾病等の早期発見・早期治療に繋げるため、特定健診・がん検診の個別受診勧奨を行い、受診率の向上を目指してまいります。あわせて、保健指導の充実により、適正医療と重症化予防につなげ、市民の健康保持増進を図ってまいります。
誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、高齢者や障がい者の移動手段の確保や冬期生活支援などの福祉事業を引き続き推進してまいります。新たに、ハンドル型電動車いす(シニアカー)の取得費等に助成を行い、高齢者の多様な移動手段確保を支援してまいります。
高齢者の方、介護を必要とする方、障がいがある方や生活に困窮している方の困りごとに対しては、相談支援と自立支援体制の充実を図り、これらの方々が孤立せずに必要な支援を適切に受けられ、安定的で自立した生活ができるように取り組んでまいります。
4つ目のまちづくりの柱「産業 活力のあるまち」では、収益性の高い農業の実践と、農業所得の向上を目指し、農業生産力の強化を図るため、生産規模拡大、大豆やそば等の土地利用型作物や園芸振興作物の栽培、畜産業における多角化・複合化や省力化・低コスト化への支援を行います。
また、地域農業を支える担い手の育成・確保については、「担い手総合支援対策事業」により、新規就農者の早期の経営安定化から、農業経営の改善・発展段階までの一貫した支援を引き続き実施してまいります。令和5年度は、経営の規模や指標、多様な担い手の確保及び育成、農用地の利用集積目標などを定める農業経営基盤強化促進基本構想の見直しを行うとともに、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用を明確化した目標地図を含む「地域計画」を令和6年度までに策定いたします。
農林環境の保全のため、老朽化し危険性が高まっている農業用ため池「吉沢小堤」については、令和6年度の廃止に向け「農業水路等長寿命化・防災減災事業」を活用し進めてまいります。また、豪雨災害時に水田の水をためる機能を利用して減災を図る「田んぼダム」の効果検証を行うための圃場を整備してまいります。
森林関係では、その活用と保全を図るため、森林資源情報や森林境界情報などを把握するための航空レーザ測量を関係町村等と共同で実施し、林業の成長産業化と森林の適正管理を進めてまいります。
商工業の育成・支援として、試作品の開発や新サービスの創出を支援する「試作品開発・新サービス創出支援事業」を継続するとともに、「商業地域空き店舗等出店支援事業」の対象に、新たに情報サービス業などの業種を追加いたします。
また、企業のIT人材不足の解消と業務の効率化、生産性の向上を図るため、「DX人材育成事業」を新たに実施し、市内事業者の経営安定と創業しやすい環境の整備を図ってまいります。
雇用の促進では、「人財育成推進・確保対策協議会」と連携し、市内企業が就労先として選ばれるよう、特に若年層の人材確保に向けた取り組みを強化してまいります。また、現在の工業用地の現状を踏まえ、新たな企業の進出や既存企業の拡張による一層の産業集積と、その集積効果による多様な雇用機会の創出を図るため、「新工業用地整備事業」を進めてまいります。
観光の振興として、新庄まつりを代表とする伝統的な行事や市内に点在する最上公園、エコロジーガーデンといった歴史的建造物や文化財などの魅力をさらに磨き上げ、来訪者が有形無形の文化財、歴史的建造物などに触れ合いながら周遊できるルートを構築し、観光による交流人口の拡大を図ってまいります。
産直まゆの郷の買い物客や手作り市キトキトマルシェへの来場者などでにぎわいを見せているエコロジーガーデンについては、既存の歴史的空間の維持と魅力の向上、多様な担い手による活用の推進により「さらに親しまれ、集う場所」となることを目指してまいります。令和5年度は、エコロジーガーデン第5期利用計画に基づき、ソフト事業の充実を図るとともに、全国的にも珍しい登録有形文化財を活用した道の駅として、地域の人に愛され、訪れた人が何度でも来たくなるような施設として整備を進めてまいります。
また、インターチェンジ付近の道の駅については、本市が中心となり、管内の町村及び関係団体と協議を継続してまいります。
自然災害に目を向けますと、近年の局地的な集中豪雨や地震等は、全国各地で大きな被害をもたらしています。昨年は、県内初となる大雨特別警報が置賜地方に発令され、5つの観測地点で24時間降水量が観測史上最大を記録し、浸水などによる建物や道路・鉄道への被害が発生しております。また、年末には、短時間の大雪に警戒を呼びかける「顕著な大雪に関する気象情報」が最上地方を含む県内に初めて発表されました。
このような、大規模自然災害から市民の生命と財産を守るため、5つ目のまちづくりの柱「生活環境 安全・安心で美しいまち」では、防災体制の強化、災害に備えたインフラの整備、消防体制の充実を図ってまいります。また、土砂災害警戒区域内の避難行動要支援者の個別避難計画を作成し、災害発生時に迅速かつ的確に行動できるように促してまいります。
また、交通事故や犯罪が起きにくい環境が整備され、安全・安心に暮らすことができるように、交通安全・防犯活動の推進に力を入れてまいります。
生活環境保全と循環型社会を推進するため、自然環境の保全や地球温暖化の防止に向けた市民意識の醸成を図ってまいります。同時に、ごみの減量化と、プラスチックを資源として循環させる取り組みを促進させるため、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集や再商品化に向けた仕組みについて関係機関と研究してまいります。
6つ目のまちづくりの柱「都市基盤 快適な暮らしを支えるまち」では、道路網の充実を図るため、日常的なパトロールや計画的な改良工事などを行い、市道機能の維持保全に努めてまいります。
今シーズンは年末からの大雪でスタートしました。本市において克雪は長年の課題であり、その対策として、冬期間の安全な交通確保と住民生活の維持を図るため、市道及び生活道路の除排雪の充実に努めるとともに、流雪溝や防雪柵の整備を推進してまいります。令和5年度は、第2次新庄市総合雪対策基本計画に基づき、2つの地区において流雪溝の整備を推進します。また、大変好評を得ている「小型除雪機等購入費補助制度」や雪国に適した支援制度にも取り組みながら、克雪対策を推進してまいります。
住みやすい都市形成に向けて、都市計画マスタープランの考え方に基づき、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、人々が安心して住み続けることができるコンパクトで魅力あるまちづくりを目指す立地適正化計画の策定を進めてまいります。令和5年度は、居住環境の向上と移住・定住の促進を図るための「住宅リフォーム補助事業」を継続するとともに、新たに空き家等を除却する費用の一部を補助する「空き家等除却支援事業」と、中心市街地にある空き家・空きテナント等のリノベーションによる東北農林専門職大学(仮称)の学生のための住居の供給を促進する「準学生寮供給促進事業」を実施してまいります。
公園整備に関しましては、歴史的風致維持向上計画に基づき、重点区域の核となる新庄城址・最上公園一帯の再整備を進めてまいります。「歴史・文化の継承と新たな都市空間の創造」をコンセプトに、周辺と一体感のある新庄城址としての歴史を感じられる空間に再整備することで、市民に愛される、賑わいのある都市公園としてまいります。
市営バス「土内線・芦沢線」、「まちなか循環線」については、コロナ禍において、感染症拡大防止対策を講じたうえで、安全な運行に努めてまいりました。まちなか循環線は、乗り方教室などの利用促進に向けた普及啓発の取り組みにより利用者は増加傾向にありますが、さらなる利用者の利便性向上のため、県立新庄病院移転にあわせ、路線改編を行うとともに、交通分野におけるデジタル化の一つである交通系ICカード導入に向けて検討を進めてまいります。
上水道事業については、人口減少社会においても、安全・安心な水道水を安定供給するため、水道ビジョンに基づき老朽化した管路や水道施設の更新、耐震化を計画的に実施してまいります。
下水道事業については、本市の生活排水処理施設普及率が県平均を下回っていることから、引き続き普及率の向上を図りながら、生活排水の適正処理に取り組んでまいります。また、快適な生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道事業計画に基づき汚水管路の整備を行い、下水道整備率の向上を図ってまいります。
7つ目のまちづくりの柱「シティプロモーション 選ばれるまち」では、住民の欲しい情報が、正しく伝わることが重要であるため、住民に確実に、わかりやすく伝える手段を的確に選択し、戦略的な広報を推進してまいります。特に、行政・防災面の情報発信では、情報が届きにくい高齢者の方などを意識した丁寧な情報発信に努めてまいります。
魅力ある地域として選ばれるまちを目指すため、本市固有の歴史的風致や歴史的建造物、食や自然といった地域の魅力をさらに高め、様々な手法で情報を発信することで、市のイメージアップを図ってまいります。さらに、関係機関と連携し、仕事や住まいに関する情報や、市の魅力に関する情報の発信を強化することにより、移住・定住に繋げてまいります。また、県外からの移住世帯の住宅取得を支援する「移住世帯住宅取得助成事業」を新たに実施するとともに、移住体験などを企画しながら、県外の移住検討者に向け、本市を移住先として選択していただけるように、積極的に働きかけてまいります。
新庄の魅力の発信として、しんじょう観光大使をお願いしております今村翔吾さんや山本哲也さん、また、企業や大学、ふるさと応援隊などで交流をいただいております様々な方々との関係を大切にし、これからも市や市民と多様に関わりのある方々を増やす取り組みを継続してまいります。
8つ目のまちづくりの柱「行政経営 将来にわたって持続可能なまち」では、地域課題を地域と行政が連携して解決できる体制の整備を目指してまいります。
新しい時代を担う職員の育成のため、「第3期新庄市人材育成推進プラン」に基づき、人材育成推進体制の整備や多様な人材を活かした戦略的な組織運営などに取り組み、時代の変化を捉え、広い視野を持ち、市民の視点に立ったまちづくりが行える職員を育成してまいります。
効果的・効率的な行財政運営を目指すため、「第7次新庄市行財政改革大綱」や「新庄市中期財政計画」などの個別計画に基づき、業務の効率化や健全な財政運営に向け取り組んでまいります。
近年、情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)が飛躍的に進化し、デジタル技術が急速に発展・普及しております。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、オンラインサービスやキャッシュレス決済の利用が増加し、テレワークの推進などのデジタル化の流れが急加速しております。
国においては、地方創生に向け、デジタルの力で地域の社会課題を解決し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を実現するデジタル田園都市国家構想総合戦略を策定いたしました。
市においても「市民サービス向上を実現するためのDX推進」、「行政の効率化を実現するためのDX推進」、「地域活性化を実現するためのDX推進」を基本方針とするデジタル化推進基本計画に基づき、デジタル技術の利用・活用により「誰でも便利にサービスを利用できる新庄市」、「職員一人ひとりが生き生きと働きやすい市役所」、「誰もが住み続けたくなる新庄市」となるよう、市役所に来庁しなくてもよい行政手続きなどのデジタル化の取り組みを積極的に展開してまいります。
5.おわりに
新年度を迎えるにあたり、市政運営に関する基本的な考え方と、主要な事業についての概要を申し上げました。
私は就任以来一貫して「元気」と「やさしさ」があふれるまちづくりに取り組んでまいりました。「まちづくりは人づくり」、自らが住むまちを「このまちは誰のもの」、「ここは私たちが住むまち、暮らすまち」という意識を持ちながら、誇りと自信を持った市民がいることが新庄市の一番の財産であると感じています。
誰一人取り残さないまちを目指して、近年は、「障がい者にやさしいまちづくり」を政策のキーワードに掲げ、市役所が、そして職員が職務において何ができるのかを常に考え行動するように促してまいりました。市政運営の指針でも申し上げましたとおり、少子高齢や人口減少が進む中、さらに新型コロナウイルスによって、市民の暮らし方や働き方が変化し、テレワーク、DXなど、デジタルテクノロジーも日々の生活に浸透してまいりました。
このような中、新庄のあるべき姿を、もう一度検証する機会として「歴史的風致維持向上計画」を捉え、進むべきまちづくりの道しるべとして活用し、私たちが受け継いだ歴史を大切にしながら、「住みよさ」をかたちにすることで、市民一人ひとりが豊かさを実感できるまちを目指してまいります。
最後に、市民の皆さまに役に立つ所が「市役所」であります。「まちは市民のもの」という自覚のもとに、「市民第一主義」を引き続き強く意識しながら、本当に住みやすく住んで良かったと思えるまちを目指し、大きくジャンプできるよう、職員一丸となり、市政運営に取り組んでいく決意を表明し、令和5年度の施政方針といたします。

このページに関する問い合わせ先
総合政策課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
電話番号:0233-22-2115
広報・地域づくり係
電話番号:0233-22-2116
システム統計係
電話番号:0233-22-2118

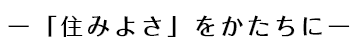
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。