令和7年度の市政運営に関し、施政の基本方針を申し上げ、議員各位をはじめ、広く市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
1.はじめに
私にとりましては、市長という大役を拝してから2回目の当初予算の編成となります。市長就任以来、「対話と決断」、「未来への責任」を基本理念として掲げてまいりました。急激な人口減少を背景として、市民生活や産業振興などあらゆる分野で今までにない深刻な課題が顕在化している現状にあります。これら諸課題の克服に新しい発想とスピード感をもって取り組んでいく決意で「輝く未来へ 挑戦するまちづくり」のスローガンのもと危機感をもって、今回の予算を編成したところであります。
現下の本市を取り巻く状況を見ますと、急激な物価高騰が進行し、地域経済や市民生活に大きな影響を及ぼしています。大企業を中心とした大幅な賃上げが進む一方で、中小企業や小規模事業者にとっては深刻な人手不足と人件費の増加が経営上の大きな課題となっています。
また、全国的な人口減少問題は、さらに深刻さを増しています。令和6年の本市の出生数は150人を下回り、想定を大幅に上回るペースで少子化が進行しており、少子高齢化が地域社会の維持にとって大きな構造的問題となっています。このような状況を乗り越え、若者や子育て世代が自らの未来と地域の将来に希望と夢を持って暮らしていけるよう、また、高齢者にとって安全で安心できるまちとして、新庄市の魅力をさらに高め、「住み続けたいまち新庄市」を目指して今後も全力で取り組んでまいります。
このため、将来、人口が減少する中においても、希望をもって暮らしていける地域社会を構築していくため、デジタル技術などを活用しながら、効率的で持続可能な行財政運営にも努め、必要とされる良質な公共サービスを提供していく体制を整えてまいります。
次に、近年、全国で頻発している自然災害への対応についても大きな課題であると捉えております。
本市においても、昨年7月に記録的な豪雨による災害が発生し、甚大な被害を及ぼしたことから、国、県と連携しながら、一日も早い復旧に努めているところです。昨年の災害を教訓として、本市における防災・危機管理体制をさらに強化し、災害に備えたまちづくりを推進してまいります。
近年の猛暑や集中豪雨、大型台風、豪雪等のこれまでにない深刻な異常気象や自然災害は、地球温暖化が大きな原因であるとされています。この課題に対する取り組みとして、本市は昨年12月に、「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指し、市民・事業者・市が協力して脱炭素社会の実現に向けた取り組みを強化してまいります。
このため、市民生活や企業活動における再生可能エネルギー導入などの取り組みのほか、環境教育の充実や、鳥獣被害防止対策も含めた森林の維持・整備などを進めてまいります。
以上の点を踏まえながら、市民一人ひとりが自分たちの街に誇りと愛着を持つことができ、活力あふれる生活をおくることができるよう「輝く未来へ 挑戦するまちづくり」に取り組んでまいります。
2.令和7年度主要事業
次に、令和7年度の主要事業について、それぞれの施策の柱に沿ってその概要を申し上げます。
第1に「子ども・子育て支援の充実」であります。
少子高齢化が進む本市においては、若者や子育て世代が希望をもって暮らし、活躍できるよう支援の充実を図り、未来を担う子どもたちへ向けた投資を行うことが最も重要な取り組みであると考えております。このたび策定いたします「新庄市こどもスマイルプラン」に基づき、子育てに対する不安を和らげ、安心して子育てができる環境を整備するため、子育て世帯の経済的負担軽減や相談支援体制の強化、待機児童対策などの各種こども施策を総合的に推進してまいります。
その1点目として、子育て世帯の経済的負担軽減につきましては、これまで実施してきた「国民健康保険税の軽減」や「子どもの医療費の無償化」の継続はもちろんのこと、更なる保育料の負担軽減を図るため、これまで、保育料を半額としていた所得階層を無償化し、新たに保育料半額となる所得階層を拡充いたします。
また、学校給食費についても第2子半額・第3子全額補助を継続しながら、物価高騰による保護者負担の軽減を充実するため、第1子への補助額を更に増額します。
2点目として、相談支援体制の強化につきましては、現在、子育て世代の相談窓口として設置している「子ども家庭総合支援拠点」と、妊娠・出産・子育ての包括的支援拠点である「子育て世代包括支援センター」を「こども家庭センター」として機能を統合し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象として、出産前から子育て期にかけて切れ目のないワンストップ型の相談支援体制の強化を図ってまいります。
3点目として、放課後に子どもが安全に過ごす居場所の一つである放課後児童クラブにつきましては、年々、利用希望者が増加していることを踏まえ、関係機関との連携・協力により、受入体制の拡充を図り、待機児童の解消に努めてまいります。
そのほか、現在、整備を進めている新中部保育所(仮称)につきましては、本市の中心的な役割を担う保育施設として保育士の研修機能の充実や集団保育が可能な医療的ケア児の受け入れを予定し、令和8年度の開所を目指してまいります。また、子育て世帯のニーズ調査や様々な方面からのご意見として、屋内型の子育て支援施設整備のご要望をいただいておりますので、この施設整備の在り方や方向性について検討を進めてまいります。
学校現場においては、年々、児童生徒数が減少する一方で、特別な支援を必要とする児童生徒が増加している現状にあります。今後、福祉分野と教育分野の連携を図りながら、本市の教育の重点施策の一つとして特別支援教育に継続して取り組み、そのための支援体制を更に強化してまいります。
また、妊娠を希望する方への支援としては、不妊治療費への助成制度を継続しながら、新たな妊産婦への支援として、県立新庄病院と連携した宿泊型産後ケアを実施することにより、出産後の母親と赤ちゃんをサポートし、育児への負担軽減を図り、お子さんを望む家庭への支援を強化してまいります。
第2に「医療・福祉の推進」であります。
令和5年に新しい県立新庄病院が開院し、高度医療の提供体制が確保されるとともに、地域救命救急センターが設置されました。さらに、新庄市最上郡医師会の協力のもと充実した夜間休日診療の体制が構築されております。
しかしながら、市民の安心・安全のためには一次医療と二次医療が機能的に連携した地域医療の体制を構築することが重要であります。そのためには、市民の日常的な診療や疾病の予防のための「かかりつけ医」の普及と定着が非常に重要でありますが、現状では「かかりつけ医」を担う医師数の不足と高齢化、さらには診療科の偏りなどへの対応が課題と捉えております。こうした課題に取り組むため、必要とされる診療科目や医療と福祉分野における市民サービスの需要などを把握するニーズ調査を行いながら、市民が安心して医療を受けることができる地域医療体制の確保を目指してまいります。
次に、健康寿命の延伸に向けた取り組みとして、特定健診やがん検診の受診率の向上を図るとともに、疾病の早期発見や生活習慣の改善による重症化予防に努め、健診後の健康相談や健康教育を強化してまいります。また、新たに骨粗しょう症検診費用を助成するほか、40歳及び50歳の節目の特定健診費用を無償化し、健診を受けやすい環境づくりに努めてまいります。
また、在宅医療と介護サービスの連携による切れ目のない支援を充実させるため、最上8市町村で運営する在宅医療・介護連携拠点「@(あっと)ほーむもがみ」において退院後のサポート体制を構築しており、病気や加齢によって生活に不安のある方が地域で安心して生活できるよう、県とも連携しながら支援に努めてまいります。
さらに、様々な要因により生活に困窮する方に対し、自ら家計を管理できるように支援するとともに、住まいの確保についても支援するなど早期に生活再建ができるようサポートするための相談体制の強化を図ってまいります。
第3に「安心・安全なまちづくり」であります。
人口減少社会の中で市民が将来にわたって安心して住み続けることができるよう都市機能を維持しながら、持続可能で魅力あるまちづくりを目指し、「立地適正化計画」を策定いたしました。今後は、この計画に沿って医療・福祉、商業などの生活利便施設や住宅の誘導、公共交通等の再構築などの取り組みを進めながら、コンパクトで住みやすいまちづくりを進めてまいります。
このような中、年々増加する空き家は、老朽化や雪害による建物の倒壊や火災の発生、犯罪の温床となるなど、周辺住民の安全を脅かしかねない存在となっています。また、空き家が放置されることは地域の景観を損ね、まちの活力を失わせる要因にもなります。一方で、良質な空き家は地域資源として活用できる可能性もあり、空き家を改修して住宅や店舗などに活用することで、地域の活性化につながるものと考えております。この課題解決に向けた取り組みを強化するため、令和7年度は空き家の全数調査により実態を把握するとともに、「新庄市住みやすいまちづくり基金」を活用し、最上地域空き家活用促進協議会とも連携しながら、空き家の利活用や除却支援、予防対策など総合的な空き家対策を集中的に推進し、住みよいまちの再生と活性化を進めてまいります。
次に、雪対策につきましては、冬期間の安全な交通確保と市民生活の維持を図るため、市道及び生活道路の除排雪の充実に努めるとともに、流雪溝の整備を推進してまいります。高齢者及び障がい者の玄関前除雪サービスは、豪雪地帯の本市において、冬期生活の負担軽減を図る上で必要不可欠なサービスでありますが、このサービス提供に必要な人材の不足が課題となっています。このため、除雪ボランティアとの連携を強化するなど、引き続き、支援体制の構築に努めてまいります。
また、近年、自然災害が全国で多発していますが、当市においても昨年7月、かつてない豪雨災害に見舞われました。こうした災害の規模拡大や危機事案の多様化を踏まえ、本市の防災・災害対策を強化することが必要と改めて認識したところであります。このため、災害や感染症など有事への初動対応に加え、全庁対応に係る指示等を担う防災危機管理の専門部署を新設するとともに、新たに災害対応に関する専門知識を有する地域防災マネージャーを任命し、災害発生時に迅速かつ的確に対応できるよう組織を強化してまいります。また、自主防災組織の活性化や避難所の在り方の検討など地域防災力を高めるための取り組みを進めてまいります。
さらに、市内全域のハザードマップの見直しや防災備蓄物資の適正な配置、排水ポンプの追加配備など計画的な災害対策に努めてまいります。
加えて、年々、夏季における猛暑日や熱帯夜となる日数が増加していることに対応するため、昨年7月に「熱中症対策アクションプラン」を策定いたしました。この熱中症対策の重点プロジェクトとして、家庭用エアコンの購入補助や、市内の店舗や公共施設をクーリングシェルターとして活用するなど、市民・事業者・行政が一体となって熱中症対策を推進し、市民の生命・健康を守り、安心・安全なまちづくりを進めてまいります。
第4に「デジタル技術活用によるDXの推進」であります。
デジタル技術の進展により各種サービスのデジタル化の機運が飛躍的に高まる中、地方自治体の市民サービスのデジタル化についても、本格的な取り組みが求められています。本市のデジタル化推進計画では、市民サービスの向上、行政の効率化、地域活性化の3つの柱を実現するためのDXの推進を基本方針としております。
まず1点目の市民サービスの向上を実現するためのDXとしては、本市においても、マイナンバーカード等のデジタルの力を最大限に活用することで「書かない窓口」を実現し、窓口手続における市民の利便性向上を目指してまいります。
また、各種証明書のコンビニ交付については、期間限定で大幅に交付手数料を減額するキャンペーンを実施することにより、マイナンバーカードやコンビニ交付の利便性の周知を図り、より一層の利用拡大と市民サービスの向上に努めてまいります。
次に2点目の行政の効率化を実現するためのDXとしては、生成AI等のデジタル技術の活用による業務の効率化と職員の負担軽減を図ることで、より専門的な業務に人的資源を集中し、更なる行政サービスの向上につなげてまいります。
さらに、3点目の地域活性化を実現するためのDXとしては、本市の基幹産業である農業分野において、農業従事者の減少と生産水準の維持に対応するため、デジタル技術を活用したスマート農業に取り組んでまいります。このため、本年2月に、本市と東北農林専門職大学、南東北クボタの3者による連携協定を締結し、スマート農林業に関する地域サービスの向上と普及拡大や研究開発、人材育成など地域創生の実現を目指す取り組みを推進していくこととしたところであります。
さらに、令和7年度当初予算において、情報通信環境の整備に向けた調査、計画策定を実施し、農業インフラの管理の省力化・高度化を図るためのスマート農業の実装を推進してまいります。
これに加え、将来的にさらに情報通信環境の整備が進むことで、農業分野以外への活用も想定されることから、さらなる調査・研究を進めていきたいと考えております。
また、教育分野においては、市内の小中義務教育学校の全ての普通教室に大型モニターを導入し、児童生徒のタブレット端末と連動した授業が行えるような環境整備を進めるとともに、学習支援ソフトも併せて導入するなど、子どもたちが学びやすい環境の充実に努めてまいります。
このような行政のデジタル化の推進のためには、民間企業などから専門的な知見を有する人材を招聘し、積極的に活用することが重要であります。本市におきましても、高度な専門性と経験を有するデジタル人材を外部から登用し、職員の意識改革、システム導入時の助言、さらには次期デジタル化推進計画策定のサポートなどを通じ、実効性の高いデジタル化を全庁的に推進してまいります。
第5として「ゼロカーボンシティ・環境保全の推進」であります。
昨年12月に、本市は「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すことを表明いたしました。将来にわたって市民が安心して暮らすことができる環境を次世代に引き継ぐため、市民や事業者の皆様と連携して地球温暖化対策を積極的に推進し、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでまいります。
この実現に向けては、市民、事業者、市が一体となって環境に対する意識を高め、より効果的な地球温暖化対策の取り組みを推進するため、地球温暖化対策実行計画を策定し、本市の自然的社会的条件に応じた自然環境の保全、市民生活への再生可能エネルギーの導入支援、事業者の省エネ対策支援、環境教育の推進、公用車への電気自動車の導入など、カーボンニュートラルに向けた取り組みを推進してまいります。
第6に「未来につながる ひとづくり・産業振興・観光交流」であります。
若者を中心とした市民がまちづくりへ参加することを促進し、地域の活性化を図るため、ガバメントクラウドファンディングを活用したふるさと納税の寄附金を原資とし、地域の活性化や地域課題の解決につながるような活動を行う個人や団体に対し補助金を交付し、未来を担う若者の活躍を後押ししてまいります。
次に、産業振興についてでありますが、人口減少に伴う人手不足、エネルギーや原材料の物価高騰や人件費の高騰、デジタル技術への対応、更には環境意識の高まりへの配慮など企業活動を取り巻く環境は急速に変化しております。本市が持つ資源や強み、ポテンシャルを活かし、企業も地域経済全体も将来にわたって持続可能で成長していく産業の振興を目指していくことが重要であると考えております。
そのためには、人手不足や企業活動のコストアップの課題を踏まえながら、いかにして付加価値の高い企業活動を目指すかや、若者が定着する産業とはどのようなものかなど、東北農林専門職大学などの高等教育機関との産学官連携の可能性なども念頭に置きながら、将来を見据えた新たな産業施策を検討していく必要があります。このため、令和6年度に市内の既存立地企業に対して実施した立地ニーズ等のアンケート調査のデータを基に、専門業者の視点による多方面からの分析や、各企業へのヒアリングを実施し、本市における持続可能な産業施策の方向性を示す「産業振興ビジョン」を策定してまいります。その中で、魅力ある働く場づくりを推進していくことが、若者や女性が地元に定着し、地域が活性化していくための重要な要素であると考えております。
次に、エコロジーガーデンにおいて整備を進めております道の駅につきましては、名称を「新庄エコロジーガーデン原蚕の杜」とし、令和7年秋のオープンを目指しております。駐車場のほか、トイレや休憩スペースを有する情報発信施設を整備することで利便性の向上を図り、エコロジーガーデンがより一層市民に愛され、魅力ある交流スポットとして親しまれるよう取り組みを推進してまいります。道の駅開業後は、指定管理者制度を活用した官民連携により、民間の柔軟な発想力と創意工夫を最大限に活かすことのできる運営手法の導入を目指してまいります。
また、インターチェンジ付近の「道の駅」につきましては、昨年から最上8市町村による勉強会を開催し、行政としての主要課題などの整理を行っておりますが、引き続き、より具体的なコンセプトや必要な機能、官民連携のイメージなどについて具体的検討を進めてまいります。また、民間組織では道の駅と連携したDMOについて研究をしていると伺っておりますので、官民連携により早期の検討会の再開を目指して取り組んでまいります。
次に、観光交流についてでありますが、訪日外国人旅行者数は、近年の円安などを追い風として過去最高を記録するなど、アジア圏を中心としたインバウンドが盛り上がりを見せております。令和5年に国際友好交流協定を締結した台湾の南投県草屯鎮との交流事業につきましては、昨年7月に私が団長となり、新庄市訪問団が台湾草屯鎮への表敬訪問を行ったほか、市内の小学生も現地の子どもたちとスポーツを通した交流を行いました。令和7年度については、この交流の流れを加速させるため、アウトバウンドの促進に向けて草屯鎮への旅行商品に対する補助制度を創設し、双方向の交流、いわゆる「ツーウェイツーリズム」の拡大を図ってまいります。
また、新たに台湾出身の地域おこし協力隊2名を配置し、台湾との交流推進を目的とした情報発信を強化するとともに、新庄の自然を生かした新たな観光コンテンツの開発など関係団体と連携してインバウンド誘致による交流の拡大を図ってまいります。
観光振興の柱となる新庄まつりにつきましては、本年、270年の記念の年を迎えるにあたり、地域固有の貴重な財産として長年受け継がれてきた伝統と市民の思いを後世に伝えるとともに、新たな歴史を刻んでいくことを目的に「270年祭記念事業」を実施いたします。
そして、いよいよ今年は、初代新庄藩主戸沢政盛公が1625年に新庄城を築城し、領内を開いてから400年を迎えます。これまでの歴史や文化を振り返るとともに、郷土新庄への愛着と誇りを高め、未来につながる人づくり、まちづくりに資するため、「新庄開府400年記念事業」を実施いたします。「歴史・文化の再認識」「次世代への継承」「交流人口・関係人口の増加」を基本コンセプトとして、次代を担う子どもたちと共に、地域のさらなる発展につなげる機会となるよう取り組んでまいります。
9月28日に実施いたします記念式典におきましては、新庄藩の歴史に関する基調講演のほか、総合アドバイザー今村翔吾氏のプロデュースによります「ダンスプロジェクト羽州ぼろ鳶組」の披露をはじめ、市民の皆様が夢や希望を抱き、新庄の未来への発展と持続可能性の創造を実感できるような内容となるよう取り組んでまいります。
このほか、開府400年記念事業として、藩祖政盛公ゆかりの自治体による戸沢サミットの開催や、市民が主体となり自ら企画提案する「市民提案事業」の実施、市内小中学生による「ふるさと探究学習事業」などを計画しております。また、名誉市民であります人間国宝奥山峰石氏の特別企画展を東京都北区と連携して開催するほか、同じく名誉市民の洋画家近岡善次郎氏の特別展の開催や新庄藩ゆかりの収蔵品などを展示する宝物展、新庄藩の歴史や文化を親子で学ぶ「親子ふるさと歴史探訪」など、新庄の歴史や文化をさらに深堀りする事業を開催する予定としております。
新庄開府400年記念事業の実施にあたりましては、市民の皆様と一体となって創る事業となるよう取り組むとともに、市内外からも多くの方々に参加いただけるよう、効果的な周知を図りながら、新庄まつり270年祭との相乗効果による一層の情報発信と誘客拡大に努め、取り組んでまいります。
最後に
私は就任当初から“対話”を通じて市民の皆様一人ひとりの声に寄り添ったまちづくりを進めていくことを申し上げてまいりました。これまで「区長と市長のまちづくり会議」を実施するとともに、希望する町内会や市民グループの皆様と対話する場として、まちづくりミーティングを開催してまいりました。今後は、さらにその機会を増やし、市民が抱えている課題やニーズをお聴きしながら、市民参加型のまちづくりを目指してまいります。
そのためには、市の情報を積極的に発信することで、市民に情報が十分届くことが大変重要であると考えております。このため、わが街ポータル「かむてんチャンネル」や市ホームページの充実、市公式LINE、各種SNSの運用など、一層の情報発信の強化を図ってまいります。さらに、ショート動画など時代の変化に応じた新たな情報発信ツールの活用にも積極的に取り組み、より多くの市民の皆様に、より効果的に情報をお届けできるよう努めてまいります。
3.おわりに
新年度を迎えるにあたり、市政運営に関しての基本的な考えと、主な事業の概要について申し上げました。
本市を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、様々な分野において克服していかなければならない課題が山積しております。人口減少が更に進行していく中、安定的かつ持続可能な行財政運営に努めながら、市民の皆様と共に「輝く未来へ 挑戦するまちづくり」に邁進してまいります。市民の皆様、議員の皆様には、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、令和7年度の施政方針といたします。
新庄市長山科朝則
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総合政策課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
電話番号:0233-22-2115
広報・地域づくり係
電話番号:0233-22-2116
システム統計係
電話番号:0233-22-2118

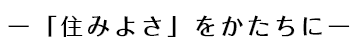
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。